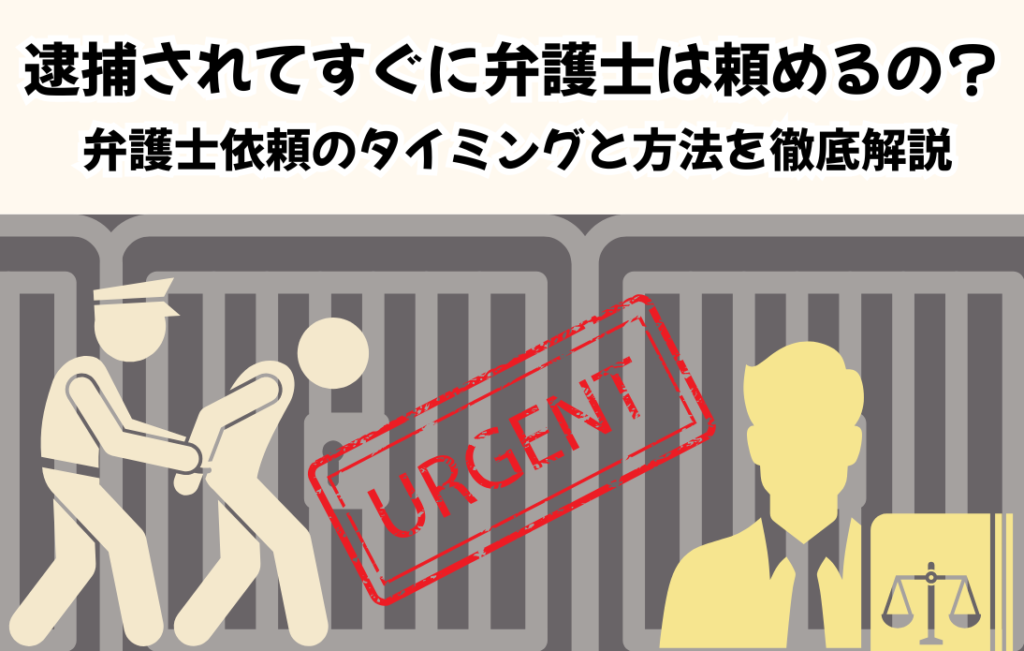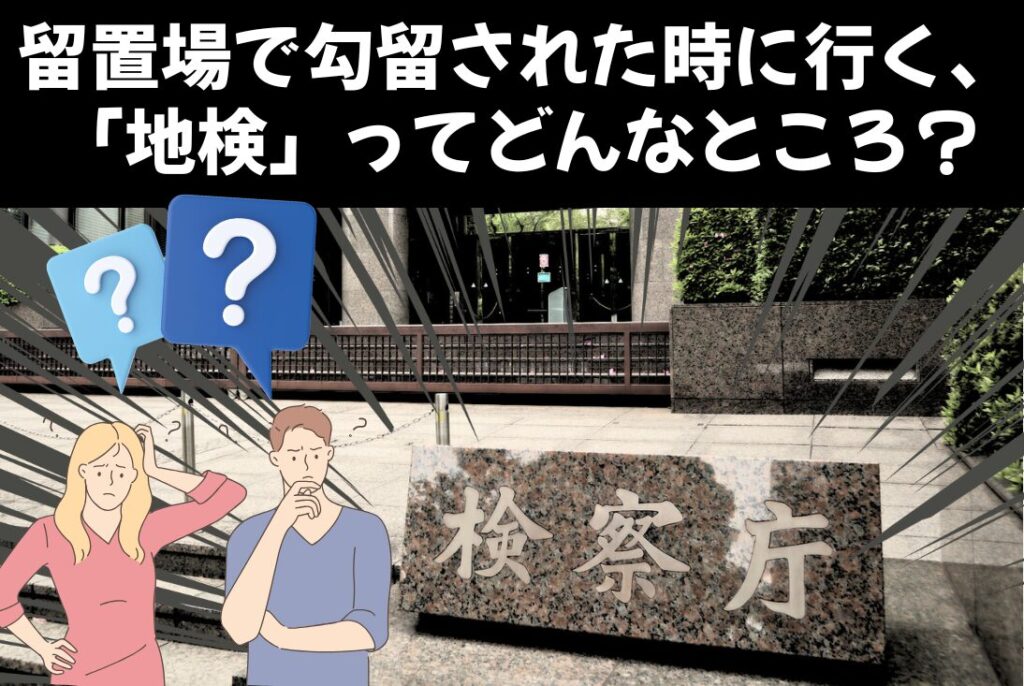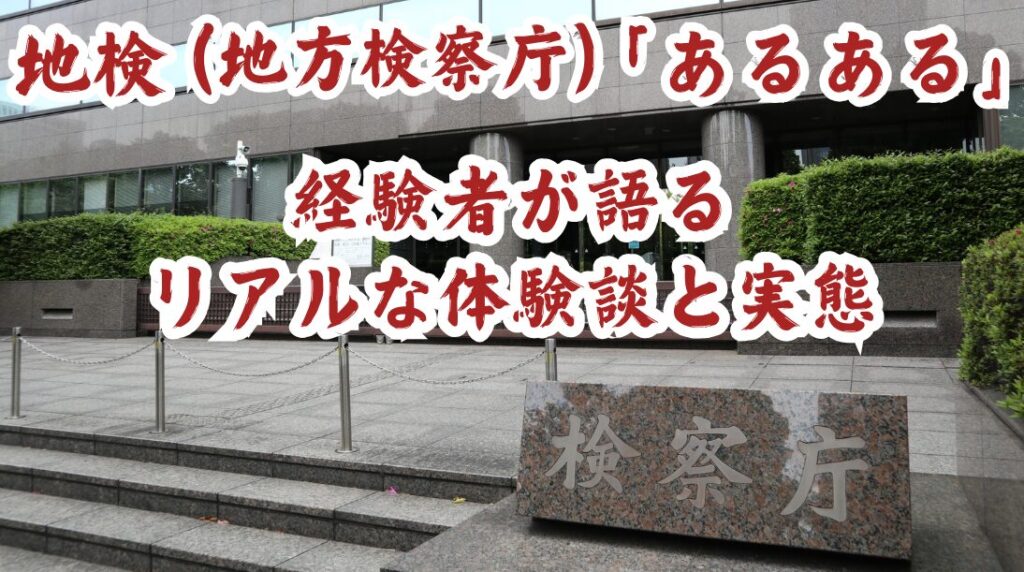留置場での勾留中に必ず、管轄の地方検察庁(地検)に行き、同行室に入り、検事による調べを待つことになります。
留置場勾留中に必ず行く地検の同行室とはどのような所なのか?
東京地方検察庁(東京地検または地検)の同行室を例にお話ししていきます。
どんな時に東京地方検察庁(地検)に行くの?
地検に行くタイミングはある程度決まっています(東京地方検察庁の例)。
- 逮捕後48時間以内に警察から検察に送致された時。
- 逮捕後48時間以内の検察送致後、検察から裁判所に勾留請求をされた時
- 10日間の勾留中に1〜2回
- 10日間の勾留延長中に1〜2回
逮捕から最大23日間、留置場にいるわけですが、その間に多い人で6回ほど地検に行き、同行室での待ち合いをします。
東京地方検察庁(地検)の同行室で待機する時間
朝9時半〜10時くらいに同行室に入ります。
そこから16時半〜18時(平均17時)まで同行室にいます。
東京地方検察庁(地検)の同行室でのルール
会話をしてはいけない
周りの人との会話は禁止されています。
留置場経験者によると、地検での会話を禁止する理由は「共犯者との情報共有を防ぐ」や「ケンカの防止」「逃走防止」のためだと説明されたそうです。
万が一会話をした場合、警察官に叱責されますし、叱責されてもなお会話を続ける場合は、別室での対応や最悪身体拘束されることもあるそうです。
会話については、地検にいる時だけでなく、地検と警察署を結ぶ、送り迎えのバスの車内でも同様に禁止されています。
両手の手錠はつけたまま1日過ごさなくてはいけない。
地検にいる間だけでなく、地検と警察署を結ぶバスの車内でも、被疑者は両手の手錠をつけたまま1日を過ごさなくてはいけません。
食事の間も両手の手錠をつけたまま食べる
食事中も両手の手錠を外してくれません。パン食中心ですが、とても食べにくいそうです。
※参考:日本弁護士連合会では、手錠を嵌めたままでの食事は人権侵害であると指摘しています。
日本弁護士連合会:検察庁内の同行室における食事中の手錠の使用に関する人権救済申立事件(勧告)
トイレは手錠を嵌めたまま行う
トイレも基本的には両手に手錠を嵌めたまま行います。
※大便の時は警察官に申請すれば、利き手の手錠を外してくれる。
トイレ内にちり紙は設置してない
トイレ内にちり紙は設置してありません。
大便をする際や鼻をかみたい時に、地検の警察官に必要な分を毎回請求します。
大便の際は水を流しながら行う
地検の同行室は古く、トイレが衝立だけで独立していないことに加え、換気扇の効きが悪いため、大便をする際は匂いが部屋に籠らないように流しながら行うように指導されるそうです。
水を飲みたい時はトイレの手洗いを利用する
水を飲みたい時は、トイレの手洗いを利用しなくてはいけないそうです。石鹸や消毒薬などは無いため、衛生面に疑問がありますし、実際水を飲むときに気持ち悪い思いをしたそうです。
地検の同行室での過ごし方
地検の同行室では様々な制限があります。
- 両手に手錠を嵌めたまま
- 会話ができない
- 本を読めない
- 座り続けていなくてはいけない
- 横の人を見たり、キョロキョロしてはいけない
上記のような制限があり、何もせず、何もすることなく時間を過ごさなくてはいけないそうです。そのためとても時間を長く感じるそうです。
地検の同行室で辛かったこと
留置場経験者に地検の同行室で辛かったことを聞いてみました。
- 直角の木の椅子に長時間座らなくてはいけなかったこと
木の長椅子で、お尻がとても痛くなるそうです。基本的に立ったり座ったりすることが出来ないので、とても辛いそうです。 - 隣の人がケンカして怖かった。
様々な罪状の人がいます。同行室は喋ることも出来ず辛い環境なので、ストレスがかかりやすくケンカも起きやすいようです。 - 待つ時間が長くて辛かった
話すことも本も読めず退屈な上に、木の椅子でお尻も痛く、なかなか時間が過ぎないそうです。検事調べや裁判所からの帰りが遅く、地検を出る時間が遅くなるととても辛いそうです。 - ご飯が食べにくかった
両手に手錠を嵌めたまま昼食を食べます。とても食べにくく、角度によって手錠が手首に食い込み痛い思いもしたそうです。 - 狭い部屋で鮨詰め
狭い部屋に余裕なく詰められるそうです。その中には風邪をひいている人や、お漏らしをしている人もいたそうです。隣の人がそういう人の時はとても嫌な思いをしたそうです。 - 手洗いの水で水を飲まなくてはいけない
水を飲みたい時は、手洗いの水を使いますが、誰からトイレを使った後に手洗いしたり、風邪をひいた人が手洗いを使ったりした後に水を飲みに行くのはかなり嫌だったそうです。衛生的にも疑問が残ります。
まとめ
留置場で勾留された時に必ず行くことになる、地検の同行室についてお話しました。
同行室は勾留請求や勾留中の検事による取り調べの際の待ち合いとして必要な部屋がですが、被疑者にとっては留置場よりも過酷な環境のようです。
※地検の木の椅子についてはこちらの記事をご覧ください!
東京23区の留置場で勾留中された時に必ず行くことになる東京地方検察庁(地検)。留置場経験者から地検の木の椅子はとても辛かったという体験談を良く聞きます。 地検の木の椅子はどのようなものなのか? イラストも交えながらお話ししていきます。
【関連記事】
- 👉 詳しくはこちら >> 地検(地方検察庁)の「あるある」:経験者が語るリアルな体験談と実態
- 👉 詳しくはこちら >> 留置場での勾留中必ず行く、東京地方検察庁(地検)の同行室の木の椅子ってそんなに辛いの?
- 👉 詳しくはこちら >> 留置場で勾留された時に行く、地検(地方検察庁)とは? どんなところ?
- 👉 詳しくはこちら >> 留置場から地検・裁判所へはどうやって行く?護送バスの内部や特徴も解説
- 👉 詳しくはこちら >> 地検(地方検察庁)の同行室のトイレ事情:逮捕・勾留後の不安を解消!
【留置場生活のリアルを知れるおすすめの書籍】
当サイト管理人による著作。留置場のリアルな生活を知りたいあなたにオススメです!
とある留置場 僕の91日間勾留記(前編)ショックと緊張の一週間
♦︎シリーズ第1弾「ショックと緊張の一週間」♦︎
ある日突然逮捕された主人公。想像もできない留置場という環境の中、襲いかかるショックと緊張の日々――。そんな非日常の中で出会った、“同じ境遇”の人々。無機質な空間で生まれる、かけがえのない絆。だが、別れはいつも唐突にやって来る――。

とある留置場 僕の91日間勾留記(中編)留置場の個性的な人々
♦︎シリーズ第2弾「留置場の個性的な人々」♦︎
ショックと緊張に満ちた一週間を経て、物語は“留置場の人間模様”へ――。そこで主人公を待っていたのは、一癖も二癖もある人々との出会いと、数々のエピソード。
長期勾留がもたらす苦悩と、保釈への希望。そして、その狭間で揺れる絶望。
前作同様、息をのむ展開から目が離せない中編――ぜひご覧ください!

とある留置場 僕の91日間勾留記(後編)留置場内トラブル
♦︎シリーズ最終章「留置場内トラブル」♦︎
「とある留置場」シリーズ、ついにフィナーレを迎える。
保釈で一度は日常へ戻った主人公。しかし、一度訪れた平穏な日常は長くは続かず、1か月後には運命の再逮捕。再び留置場の扉が開く。そこに待ち受けていたのは、過去に例を見ないトラブルと、複雑に絡み合う濃密な人間模様。限界に追い込まれ揺れ動く心、出口なき先の絶望——
シリーズ最終章、もっとも過酷な「最後の留置場」生活がここに!