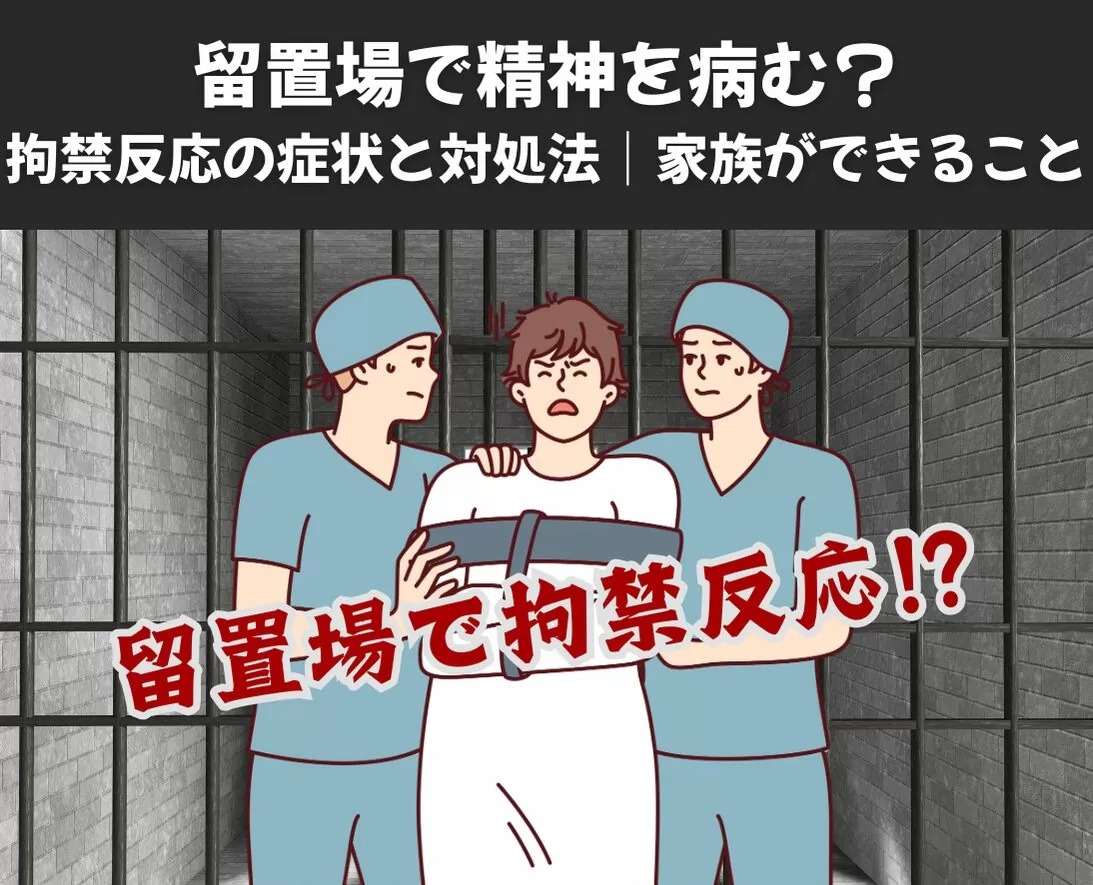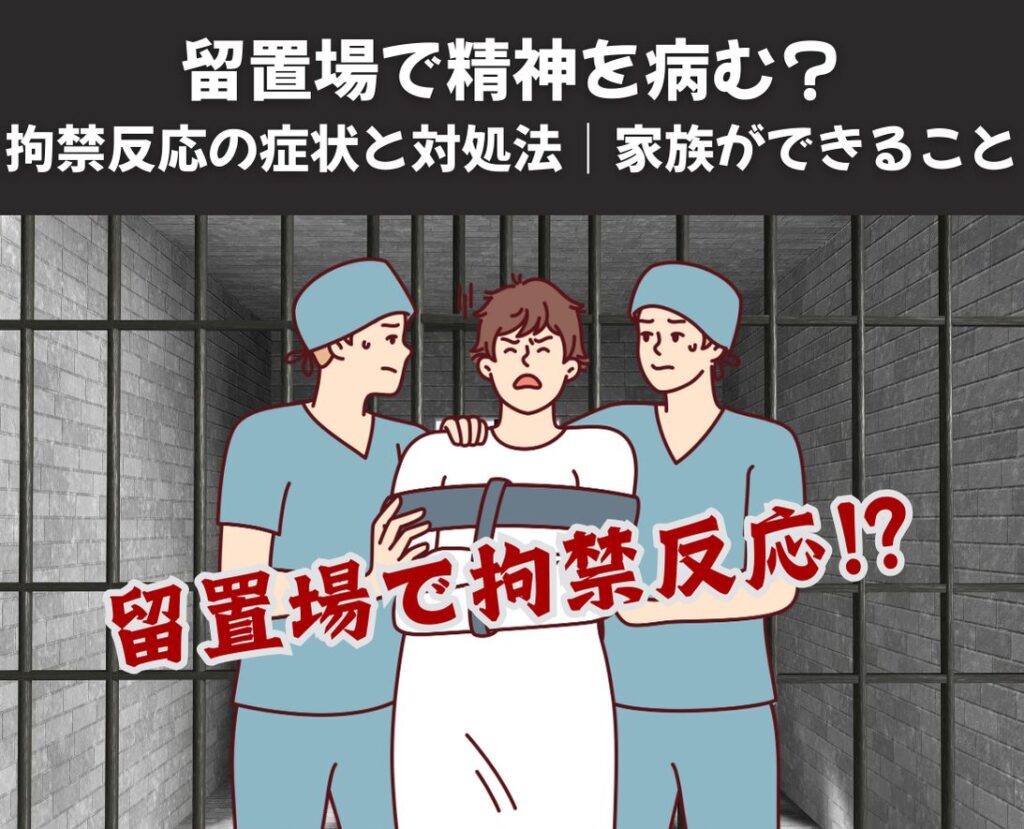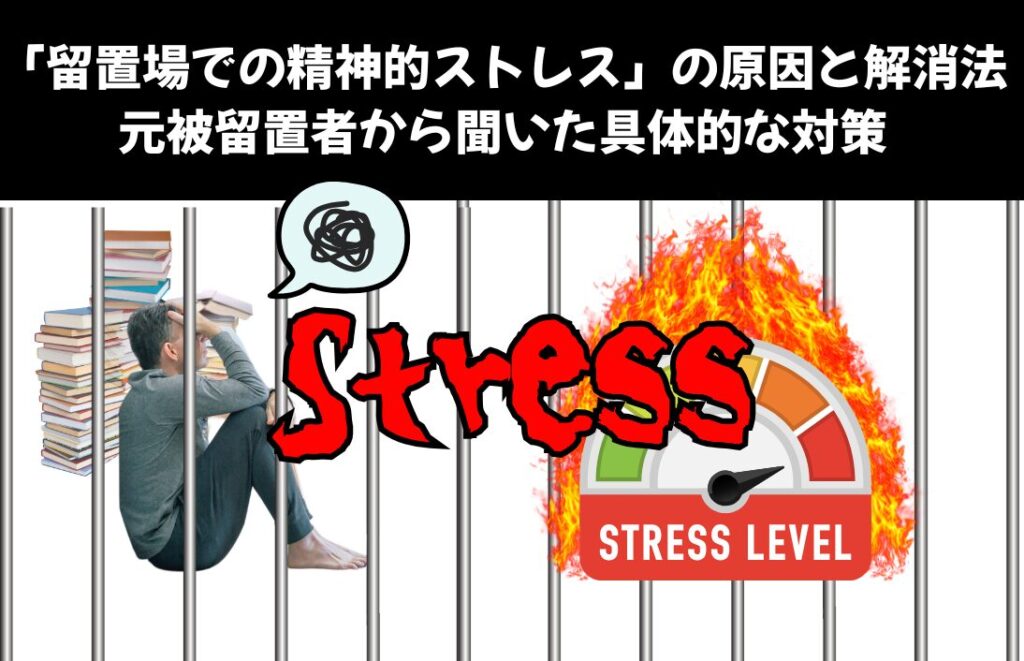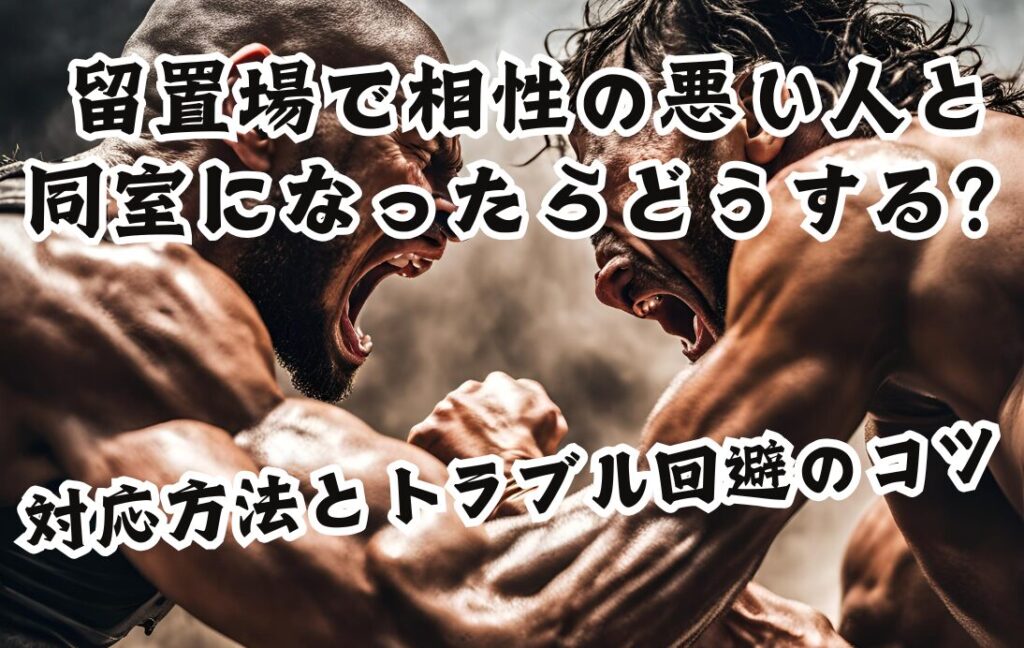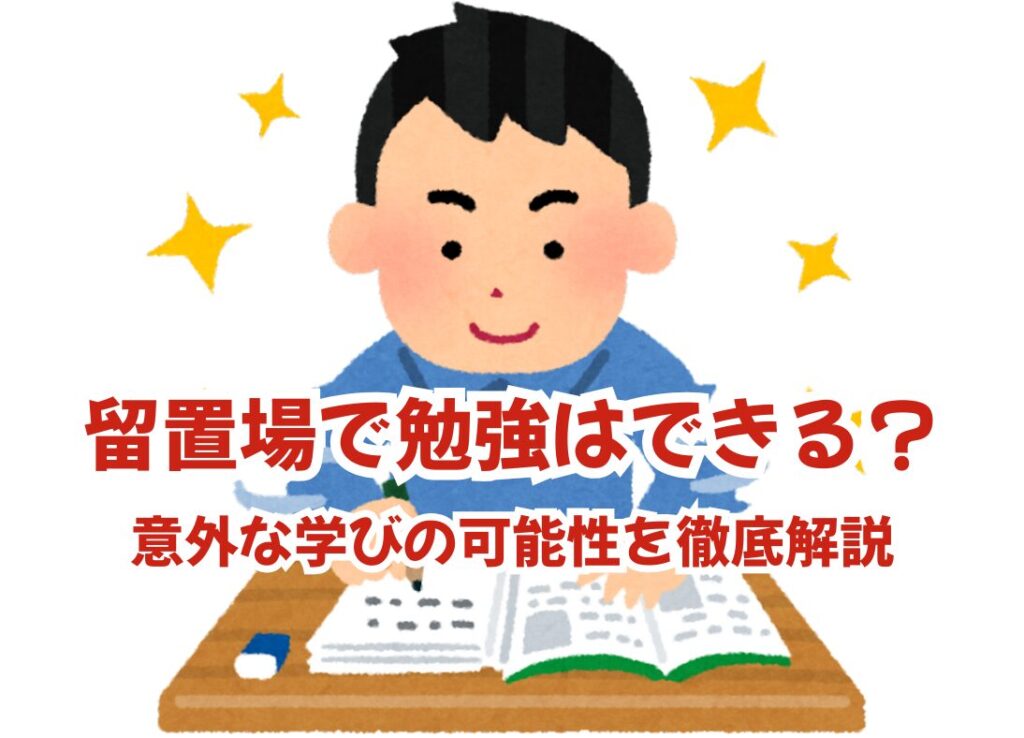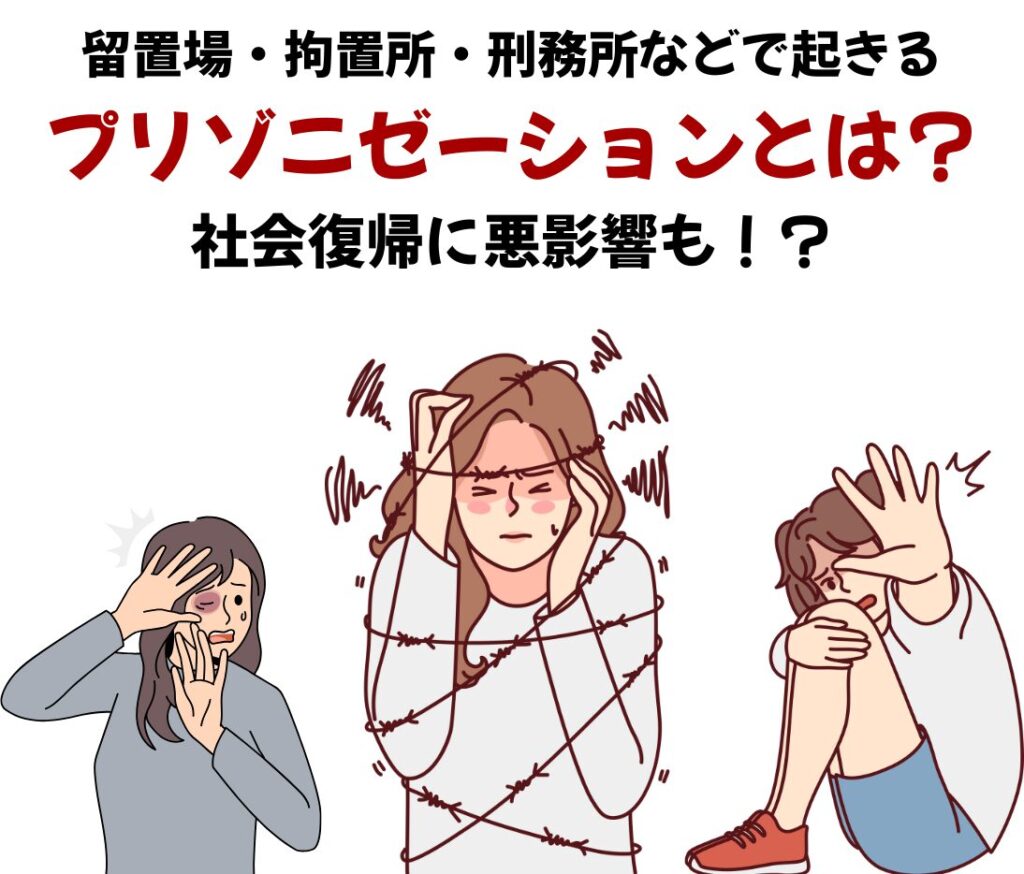
プリゾニゼーションとは
プリゾニゼーション(Prisonization)は、留置場や拘置所などの拘禁施設や刑務所などの厳しい環境に適応する過程で、収容者が個性や積極性を失い、従属的で受動的な行動を取るようになる現象を指します。
この現象は、留置場・拘置所・刑務所などでの厳格な規則や監視のもとで生活する中で生じるもので、留置場・拘置所・刑務所などの文化に適応するための心理的プロセスであり、長期にわたる拘禁生活が人間の精神や行動に与える影響を示しています。
国家公務員上級心理職として法務省に入省後、全国の刑務所や拘置所で犯罪者を分析する資質鑑別に従事していた出口保行氏はプリゾニゼーションについて次のようにコメントしてます。
刑務所ではよく「プリゾニゼーション(刑務所化)」という言葉が聞かれます。刑務所での生活に慣れてしまい、個性や積極性を失うことです。刑務所では常に職員の指示に従って行動することが求められますから、それに適応した結果です。1~2年ならそれほどでもありませんが、10年も入っているとプリゾニゼーションにより社会生活を送ることが難しくなってしまうのです。
出典:THE GOLD ONLINE 犯罪心理学者が語る…「お兄ちゃんだから我慢しなさい」と言ってはいけない理由(出口保行)
このようにプリゾニゼーションには大きな問題があります。
プリゾニゼーションの特徴
新潟青陵大学大学院の碓井真史氏によると、プリゾニゼーションの特徴と成り立ちを以下のように記しています。
自由が奪われ、圧倒的な力にねじ伏せられて、人は個性と積極性を失っていきます。病的な歪んだ「模範囚」になってしまうのです。かれらは、従属的、依存的、受動的になり、ただ言いなりに動く人間になってしまうのです。
もちろん、すぐにこうなるわけではありません。抵抗することもあるでしょう。しかし、抵抗しては痛めつけられてといった経験を長年積み重ねていくうちに、多くの人は、プリゾニゼーションに陥っていくのです。
まとめると、プリゾニゼーションによって、以下のような症状が出ることが特徴です。
- 個性と主体性の喪失:自由が奪われた環境で、自分の意思を表現する機会が減少した結果、意思表示や個性が失われてしまいます。
- 心理的影響:無気力感や虚脱感が生じ、「どうせ無理」といった学習性無力感に近い心理状態になることがあります。
- 受動的な態度:職員の指示に従うことが求められるため、自発的な行動が抑制され、自主的な行動ができなくなります。
- 社会復帰の困難:長期間収容されると、社会生活に適応する能力が低下し、日常的な行動(例:電車の切符購入など)にも支障をきたす場合があります。
- 長期勾留による深刻化:短期間では軽度の影響で済む場合もありますが、10年以上の長期拘禁では社会復帰能力が著しく低下するリスクがあります。
プリゾニゼーションが発症するリスクはどれくらい
プリゾニゼーションの発症リスクについて、具体的な統計データは提供されていませんが、以下の点が示唆されています:
- 長期囚に多く見られる傾向があります。
- 短期囚でも、模範囚型や意志薄弱・無力型の人に認められることがあります。
- 死刑囚の多くはプリゾニゼーションを免れる傾向があります。
- 拘禁環境に置かれた人々に広く影響を与える可能性があり、新型コロナウイルス感染によって一時船外への外出が禁止された「ダイヤモンド・プリンセス号」という豪華客船がありましたが、そのような良い待遇であっても、外出が出来ないことで拘禁反応やプリゾニゼーションの発症リスクがあったと言われています。また、病院への入院などによる隔離などでも発症のリスクがあると言われています。
プリゾニゼーションのリスクは、拘禁期間の長さや個人の性格特性、拘禁環境の厳しさなどによって変動すると考えられます。
ただし、具体的な発症率や統計的なリスク評価については明確ではありません。
プリゾニゼーションの具体例
書籍「日本一長く服役した男」によると、61年間服役した男性は、出所後も刑務所での生活習慣が抜けず、社会復帰に苦労しました。刑務所内での「看守の顔色を見る」「規則通りに動く」といった行動様式が体に染みついていたためです。
無期懲役囚と死刑囚の違い
- 無期懲役囚は収監後たった数ヶ月で、どんなに個性的で特徴的な人でも、脱個性的かつ無気力になり、死刑囚は「今日が最後かもしれない」という心理から逆に個性が強まり、かつ活動的になる傾向があると言われています。
プリゾニゼーションと冤罪の関係
プリゾニゼーションは冤罪被害者に深刻な影響を及ぼす可能性があります。特に、長期間拘禁された場合、以下のような問題が生じます:
- 心理的影響:
- 冤罪被害者も刑務所環境に適応する過程でプリゾニゼーションを経験し、精神的なダメージを受けることがあります。
- 自己主張や抵抗力が低下し、自分の無実を訴える意欲が失われる可能性があります。
- 社会復帰の困難:
- 長期間拘禁された冤罪被害者は、釈放後も社会生活に適応することが難しくなる場合があります。
- 例えば、書籍「日本一長く服役した男」によると、61年間の服役後も刑務所での習慣が抜けず、社会復帰に大きな困難を抱えていたそうです。
プリゾニゼーションが社会復帰に与える影響は
プリゾニゼーションは、受刑者の社会復帰に以下のような深刻な影響を与える可能性があります:
- 個性と積極性の喪失:
プリゾニゼーションにより、受刑者は個性と積極性を失い、従属的、依存的、受動的になってしまいます。これは社会復帰後の自立を困難にする可能性があります。 - 社会適応能力の低下:
長期間の拘禁により、日常的な社会生活に必要なスキルが失われる可能性があります。例えば、公共交通機関の利用方法など、基本的な生活スキルの再習得が必要になることがあります。 - 就労の困難:
プリゾニゼーションにより、職場での自主性や積極性が失われ、就労の継続が困難になる可能性があります。これに対応するため、矯正施設では職業指導や就労支援指導が行われています。 - 心理的影響:
プリゾニゼーションは受刑者の心理状態に長期的な影響を与え、社会復帰後も自信の喪失や依存的な態度が続く可能性があります。
これらの影響を軽減するため、矯正施設内での職業訓練や社会復帰支援プログラム、さらには出所後の継続的な就労支援や生活支援が重要となります。
社会とのつながりを保ち、プリゾニゼーションを防ぐための取り組みが、円滑な社会復帰には不可欠です。
プリゾニゼーションへの対応策
- 心理的ケア:
- 専門家によるカウンセリングや精神科医の診察を通じて、心理的ダメージを軽減します。
- 社会復帰支援:
- 仮釈放後には「乗車保護」など具体的な支援(例:公共交通機関の利用方法指導)が必要です1。
- 刑事司法改革:
- 冤罪防止や長期拘禁の見直しを通じて、不当な拘束による心理的影響を最小限に抑える取り組みが求められます。
まとめ
プリゾニゼーションは刑務所環境への適応過程で生じる現象ですが、その影響は個人の精神状態や社会復帰能力に深刻なダメージを与える可能性があります。
特に冤罪被害者の場合、その影響はさらに大きくなる傾向があります。袴田事件などの事例から学びつつ、適切な支援体制や司法制度改革が必要です。
【関連記事】
留置場で勾留されることは、精神的に大きな負担を伴う経験です。この記事では、留置場における心理的な影響、いわゆる「拘禁反応」について詳しく解説します。また、その影響を最小限に抑えるための方法や、家族や知人が支援する際に知っておくべきポイントについても触れていきます。