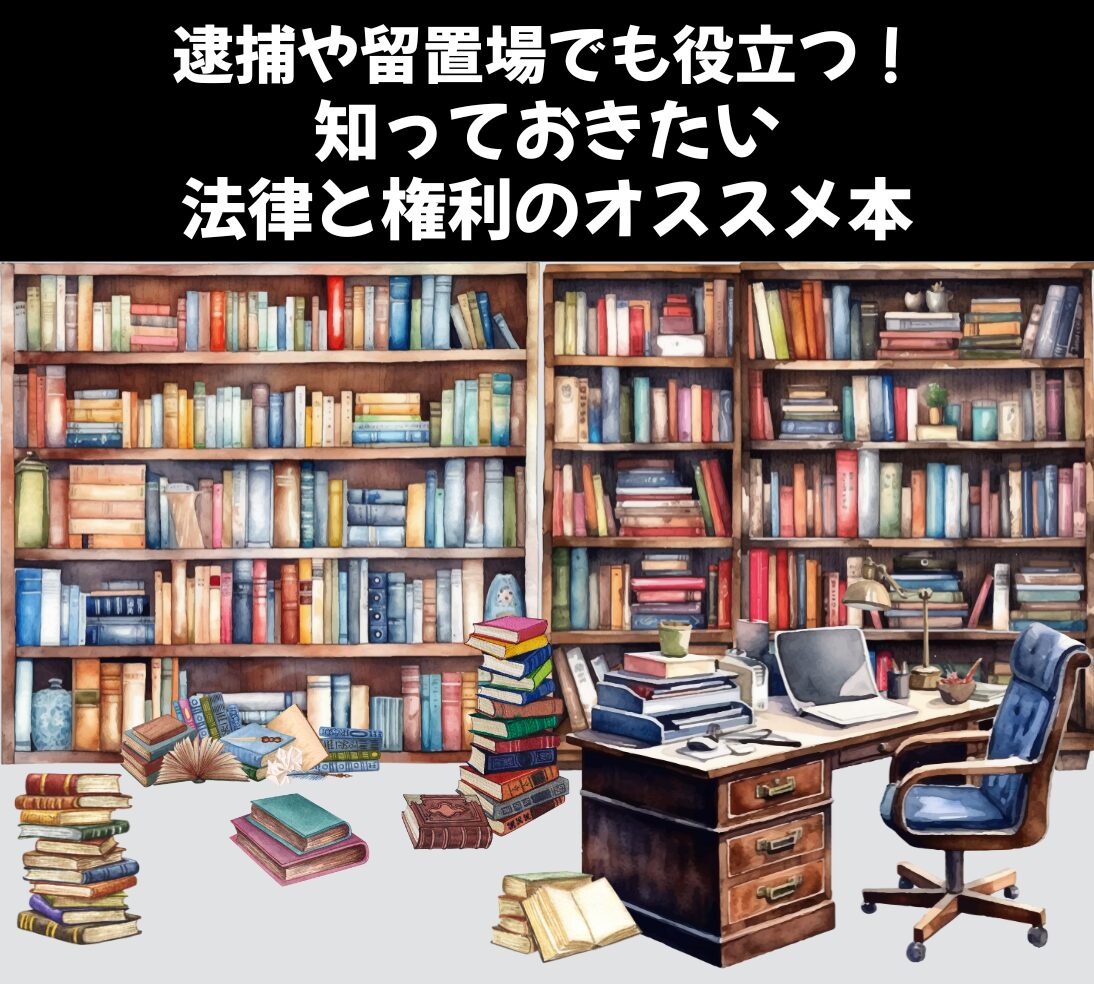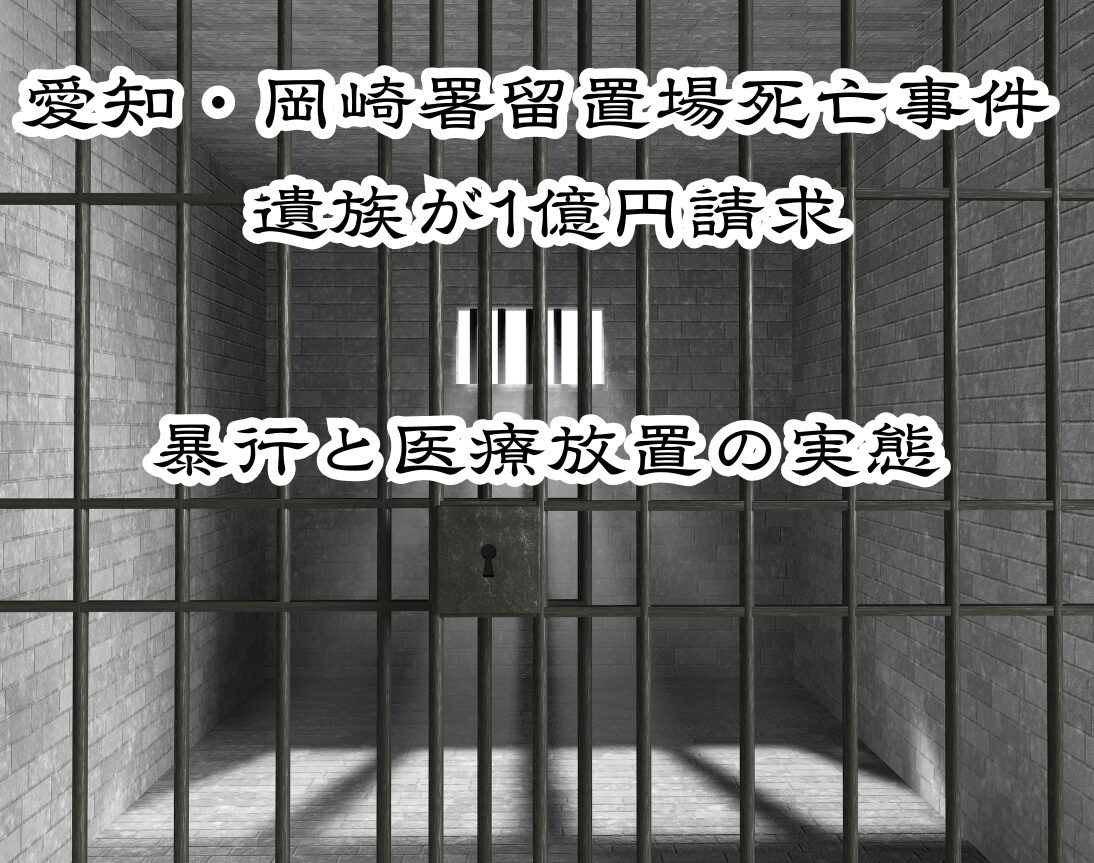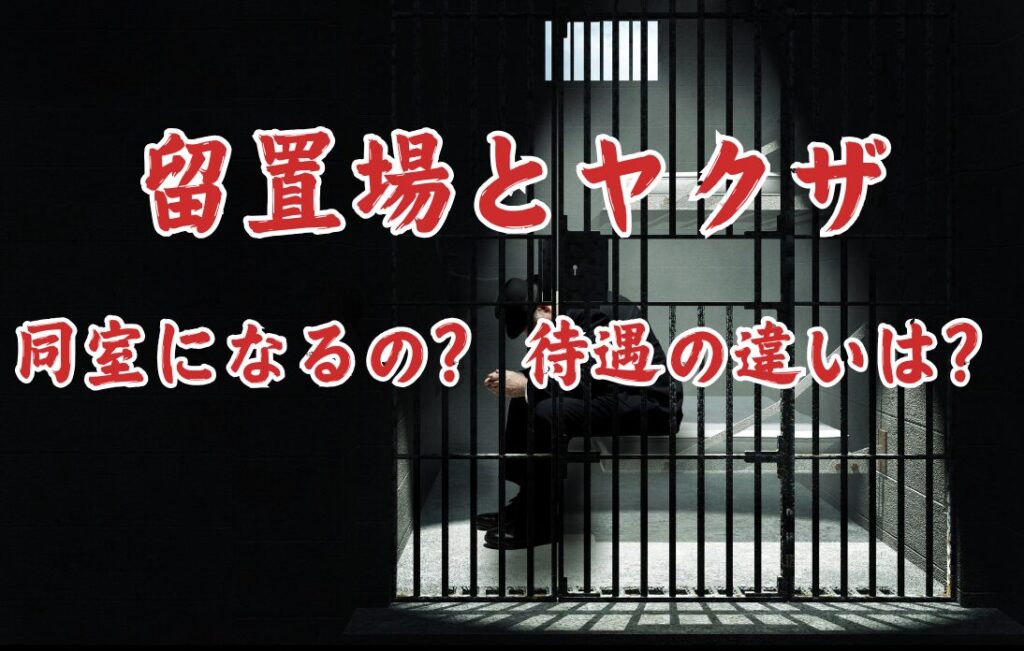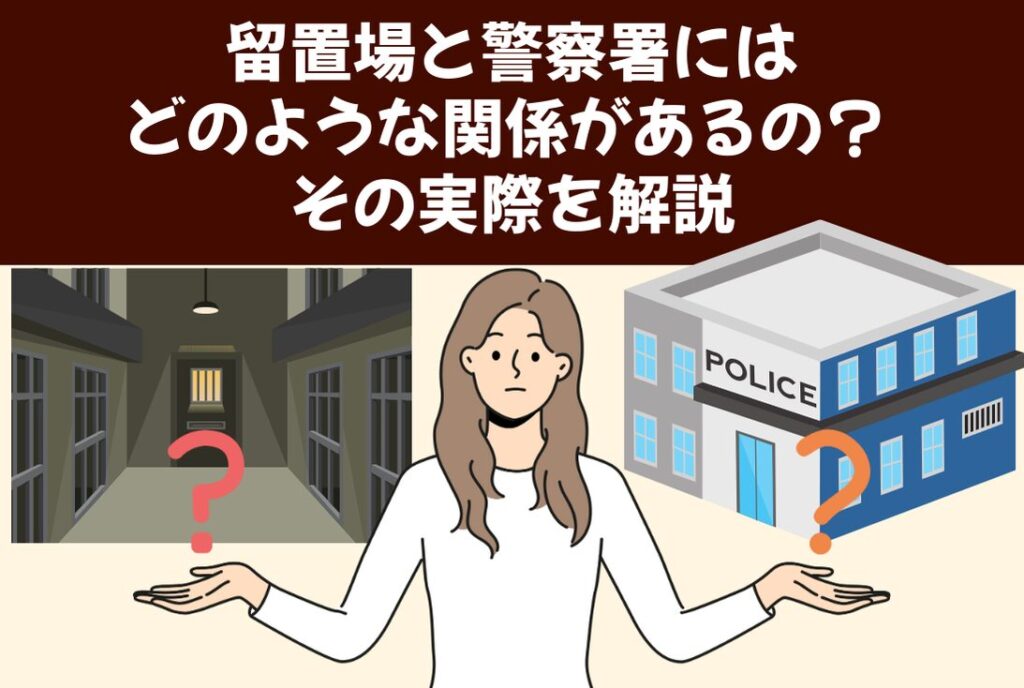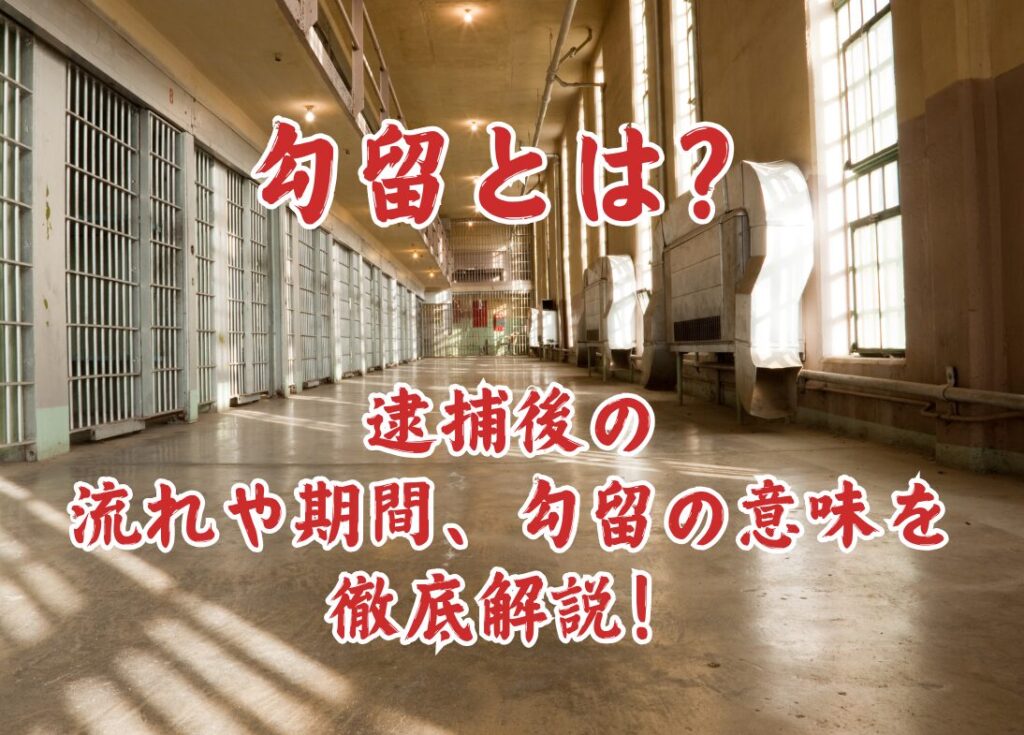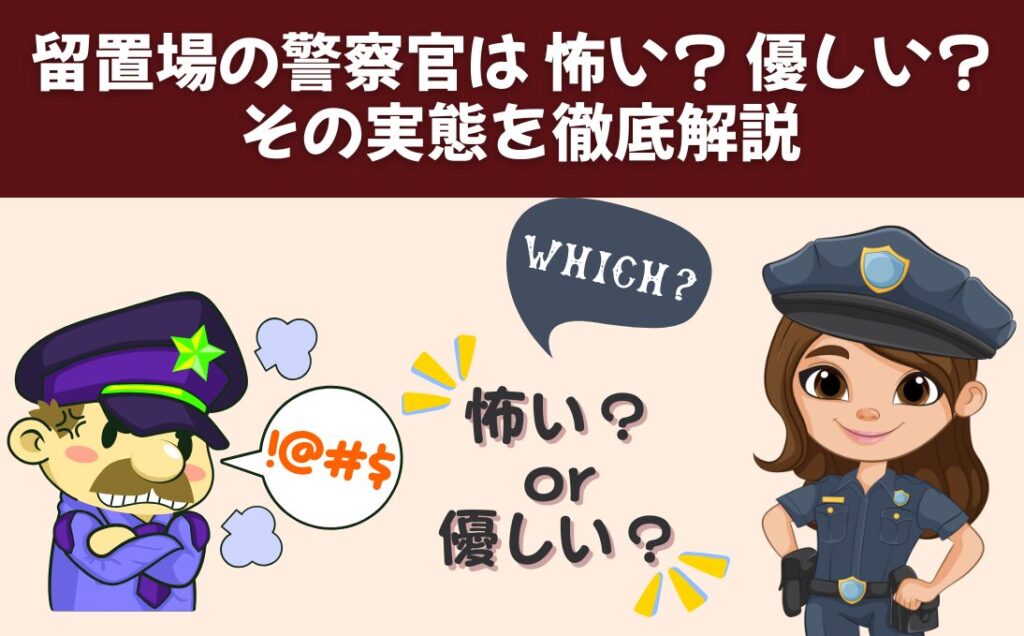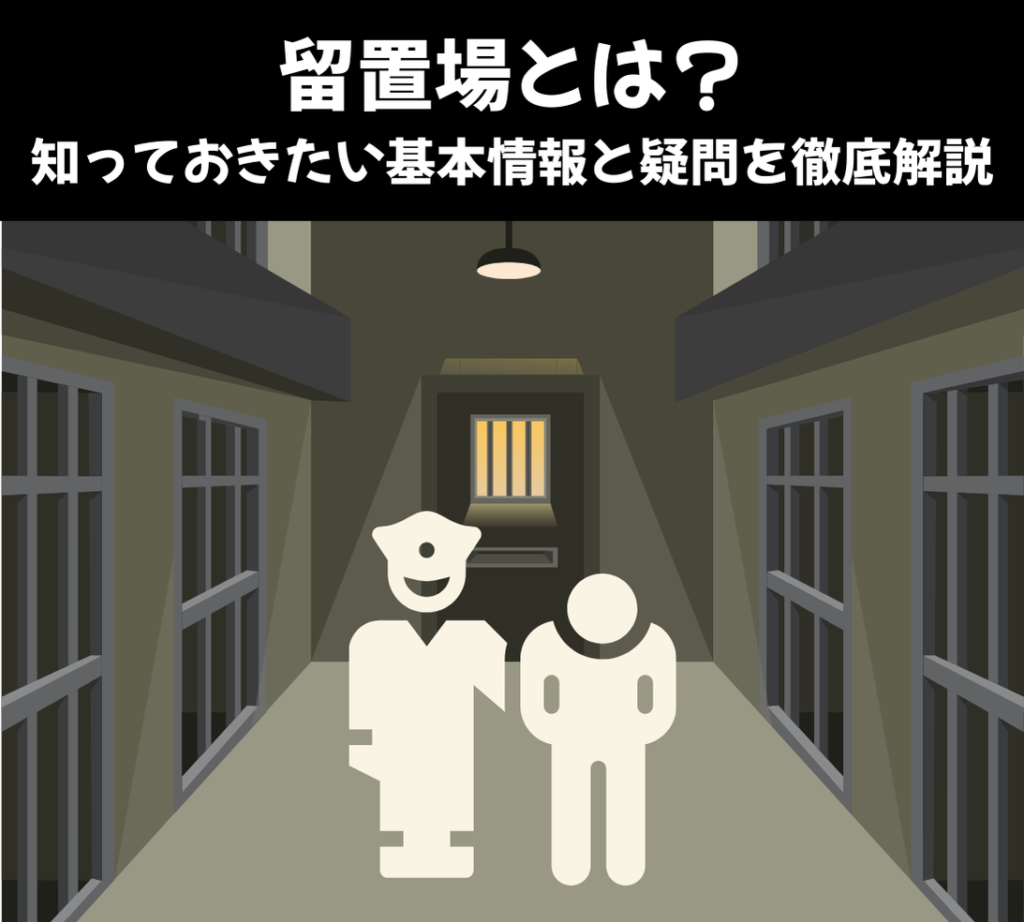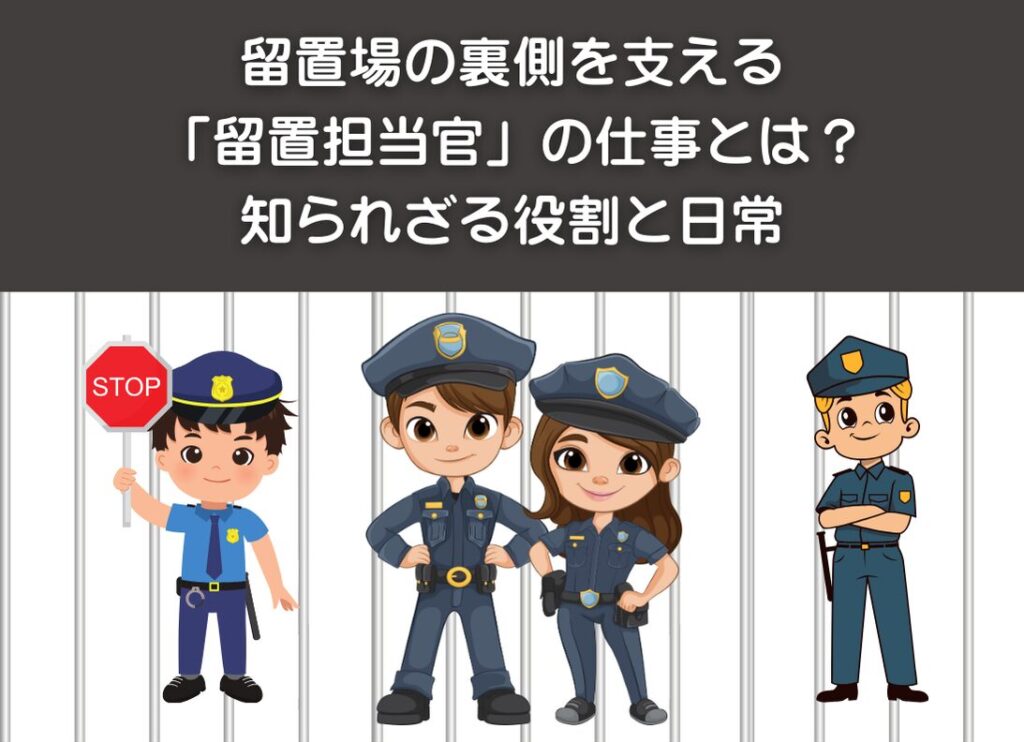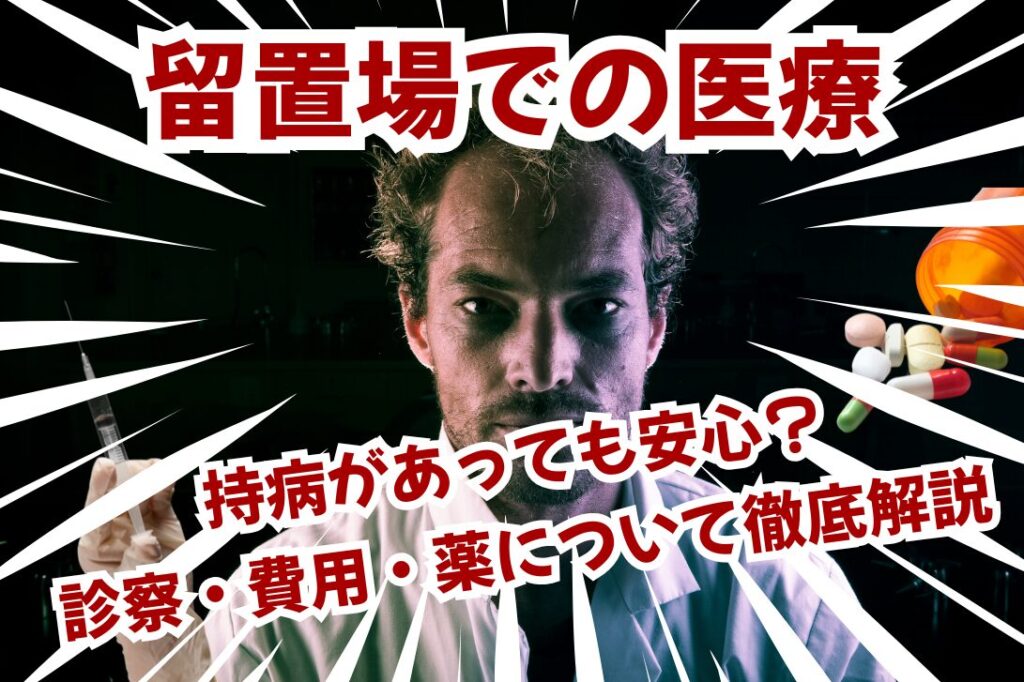
持病のある家族や知人が留置場で勾留された時、適切な医療を受けられる体制があるかどうか心配になるのではないでしょうか。
持病がある場合や、留置中に体調を崩した場合、適切な体調管理や医療を受けられるのか不安に感じる方もいるかもしれません。
この記事では、留置場における医療について、徹底的に解説します。持病がある場合の対応、体調不良時の診察や薬の服用、医療費、入院の可能性など、気になる疑問を詳しく解説していきます。
1. 留置場における医療体制の基本
適切な医療措置が受けられると定められている
留置場では、被留置者の心身の状態を把握し、適切な保健衛生上および医療上の措置を講じることが、以下のように義務付けられています。
(保健衛生及び医療の原則)
第五十六条 刑事施設においては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。
留置場経験者が語る現実
留置場経験者が語る留置場の医療の現実について、ヒアリングした内容を下記にご紹介していきます。
自由に受診できるものではありませんし、基本的には留置担当官が見た目で診察の可否を判断するので、一般的な診察からは程遠いものです。
例えば、夜も眠ねれないような歯痛があった場合に歯科受診は出来るものの、治療行為を受けるための受診ではなく、抜歯するためなら受診できるとの説明がありました。
また、たとえ辛い症状であっても、発熱程度では受診できません。せいぜい市販の日用薬(プレコールやイブなど)を飲ませてくれるだけです。
ですから、体調不良時にすぐに医療が受けられるとは思わない方がいいです。
拘置所での話となりますが、角川書店の元社長である角川歴彦氏の手記「人間の証明」では、適切な医療が受けられなかったことで「死を覚悟した」と述べています。手記を読む限り、留置場での医療についても全く同じことが言えるそうです。
角川書店の元社長、角川歴彦氏が226日もの間、東京拘置所で勾留された体験を書いた手記。留置場にも当てはまる日本独特の「代用監獄」の問題。本記事のテーマである勾留中の医療の現実についての記載もリアル。日本の捜査機関や司法制度の現実と問題を知りたい方にオススメです!
法律のトラブルはある日突然やってきます。準備なしにそのトラブルに巻き込まれると、金銭的にも精神的にも大きなダメージを負ってしまいます。法律や権利について知識を得ておくことは、自らの身を守ることにもつながります。法律や権利、日本の司法制度などについて考えるきっかけになる本を選んでみました!ぜひ参考にしてみてください!
2022年12月、愛知県警岡崎署の留置場で発生した勾留中の男性死亡事件は、日本の刑事司法制度の闇を浮き彫りにしました。 この記事では、監視カメラに記録された暴行実態や医療放置の問題点、最新の裁判動向を徹底解説します。
定期的な健康診断(医師による診察)
留置されている方は皆、月2回、委嘱医師による定期健康診断を受けることができます。法律的根拠は以下のとおりです。
(健康診断)
第六十一条 刑事施設の長は、被収容者に対し、その刑事施設における収容の開始後速やかに、及び毎年一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。刑事施設における保健衛生上必要があるときも、同様とする。
留置経験者が語る健康診断(医師による診察)の実際
実際に月2回(または週2回)、お医者さん(医師)による診察を受けることが出来ました。
診察の流れは
- 血圧測定(市販の機械)
- 問診
- 薬の処方(必要なら)
という流れでした。
特に聴診や触診などがあるわけでもなく、問診に対して薬を出すか出さないかを判断する程度のものでした。
例えば、
- 頭痛がするから痛み止めが欲しいと言えば、カロナールが処方される
- 風邪をひいたと言えば、PL錠が処方される
- 寝違えたと言えば、ロキソニンジェルが処方される
- お腹の調子が悪いといえば、整腸剤が処方される
- 眠れないと言えば、眠剤が処方される(眠剤の処方については、みんなが要望するので、断られる可能性が高い)
このようなものでした。
持病があれば、この時に処方してもらう必要があります。また、逮捕直後から薬が必要な場合は、薬の持ち込みは出来ないので、留置場に行く前に刑事同伴で病院に連れて行ってもらい、改めて薬を処方してもらう必要があります。
診察・治療
負傷した場合や病気に罹患した場合には、速やかに医師の診察を受けることができるとされています。必要に応じて、留置場外の病院での通院や入院も可能とされています。法律的根拠は以下の通りです。
(診療等)
第六十二条 刑事施設の長は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、刑事施設の職員である医師等(医師又は歯科医師をいう。以下同じ。)による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。ただし、第一号に該当する場合において、その者の生命に危険が及び、又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る。
一 負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき。
二 飲食物を摂取しない場合において、その生命に危険が及ぶおそれがあるとき。
2 刑事施設の長は、前項に規定する場合において、傷病の種類又は程度等に応じ必要と認めるときは、刑事施設の職員でない医師等による診療を行うことができる。
3 刑事施設の長は、前二項の規定により診療を行う場合において、必要に応じ被収容者を刑事施設の外の病院又は診療所に通院させ、やむを得ないときは被収容者を刑事施設の外の病院又は診療所に入院させることができる。
留置場経験者が語る診察・治療の実際は?
基本的には留置担当官の主観による判断です。
病気になっていて、「辛い」と言っても、市販薬を飲むだけで放置されることが大半です。
軽い怪我の場合も同様です。
ただし、転んで出血しているとか、頭を強く打った場合は受診または救急車対応してもらっている人がいました。
持病がある場合は、病院に連れて行ってもらえる可能性が増します。薬が切れた時はもちろん、自覚症状が増した時は連れて行ってもらえる可能性が高まります。
病院に連れて行かれるときは、逃亡を防ぐために、留置担当官3名が一人の被留置者を車で病院まで送迎します。
2. 留置場での医療費は?
公費負担が基本
留置場内での医療費は、委嘱医師による健康診断や診療の場合、公費で負担されます。言い換えれば、タダで受診できます。薬についてもタダです。
指名医による診療は自費
ただし、被留置者が希望して認められれば、委嘱医師以外の医師(指名医)の診察を受けることが出来ます。その場合は、自費となります。
(指名医による診療)
第六十三条 刑事施設の長は、負傷し、又は疾病にかかっている被収容者が、刑事施設の職員でない医師等を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、刑事施設に収容される前にその医師等による診療を受けていたことその他の事情に照らして、その被収容者の医療上適当であると認めるときは、刑事施設内において、自弁によりその診療を受けることを許すことができる。
3. 留置場で薬は飲める?
原則持ち込み不可
留置場には、原則として外部から薬を持ち込むことはできません。
持病があり、毎日服薬が必要な場合は、留置場に入る前に刑事に病院に連れて行ってもらい、改めて薬を処方してもらう必要があります。
医師の判断で処方される
持病などで薬の服用が必要な場合は、月2回の医師の診察を受け、必要と判断された場合に限り、留置場内で処方された薬を服用することができます。
薬の差し入れはできる?
家族や知人が薬を差し入れることは原則として禁止されています。
留置場に薬はある?
留置場内に日用薬は備え付けてあります。
例えば、
- 風邪薬(プレコールなど)
- 痛み止め(イブなど)
- 下痢止め(正露丸など)
- 下剤(ビューラックなど)
- その他(オロナインなど)
が備え付けてあります。
日用薬を使いたい場合は、使用したい旨を留置担当官に伝え、服用願いを記載することで服用できます。市販薬の服用はかなり気軽に請求できます。
4. 留置場にいる医師はどんな人?
委嘱医師
留置場には、警察署長等が委嘱した医師(委嘱医師)が定期的に訪れ、健康診断や診療を行います。
留置場経験者の印象だと、普通の街の内科のお医者さんが来ている印象だそうです。
専門的な治療が必要な場合
専門的な治療が必要な場合は、外部の病院の医師による診察や治療を受けることができるとされています。
ただし、留置担当官の主観による判断となるため、思うように受診することは難しいようです。
5. 留置場で体調を崩したらどうなる?
申告
まずは、留置係の警察官(留置担当官:担当さん)に体調不良を申告しましょう。
診察
症状に応じて、施設外の病院での診察を受けることができるとされています。
現実的には、日用薬で様子を見るという判断をされることが大半です。
病院への搬送
高熱、激しい腹痛、意識障害など、緊急性の高い症状の場合は、病院へ緊急搬送されることもあります。
6. 持病がある場合の注意点
事前申告
留置場で勾留される際に、持病についてヒアリングされますが、服薬が必要であれば、事前に受診する必要があるため、逮捕した刑事に持病の話をするようにしましょう。
このように、留置される前に、しっかりと持病がある旨を警察に伝えておくことが重要です。
アレルギーがある場合は、アレルギー食に変更してくれます。忘れずに申告しましょう。
情報提供
病名、服用している薬の種類、アレルギーの有無などを正確に伝えましょう。
お薬手帳を持っていくと確実です。
服用中の薬
医師の診断に基づいて、必要な薬が支給されます。
服薬の薬をもらえるタイミングは以下の通りです。
- 逮捕直後、刑事に病院に連れて行ってもらい、処方してもらう。
- 月2回の受診の際に処方してもらう。
- 例外:体調不良などで病院に受診させてもらい、処方してもらう。
気軽に受診・処方してもらえないため、あらかじめ処方してもらう薬を整理しておき、受診のタイミングで請求できるようにしておきましょう。
7. 家族ができるサポート
情報提供
持病やアレルギーに関する情報を、留置担当者に正確に伝えましょう。
差し入れ
衛生を保つための下着類や、寒さを防ぐ衣類などを差し入れることができます。ただし、留置場によって差し入れ可能なものが異なる場合があるため、事前に確認するといいでしょう。
まとめ:留置場でもある程度の医療は受けられる
留置場では、被留置者の健康状態に配慮し、適切な医療措置を講じると法律で定められています。持病がある場合は、医師の診断に基づいて必要な薬を服用することができます。
とはいえ、急な病気や怪我についての対応は、留置担当官(担当さん)の主観による判断となるため、普通の生活のように好きなタイミングで気軽に医療を受けることはできません。
家族としては、正確な情報を提供し、可能な範囲でサポートすることで、安心して留置場生活を安心して過ごせるよう努めましょう。
身体や衣服の清潔を保つことも大切ですし、留置場生活は孤独で辛いものですから、手紙や衣服の差し入れも大切です。
不安や疑問がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。適切なアドバイスを得ることで、より良い対応ができる可能性があります。
【関連記事】
- 👉 詳しくはこちら >> 愛知・岡崎署留置場(留置所)死亡事件 遺族が1億円請求|暴行と医療放置の実態
- 👉 詳しくはこちら >> 留置場に入るとどうなる? 一日の流れを紹介
- 👉 詳しくはこちら >> 留置場の食事内容は? 実際の体験談とメニュー例
- 👉 詳しくはこちら >> 【留置場】差し入れの方法と注意点
【留置場生活のリアルを知れるおすすめの書籍】
当サイト管理人による著作。留置場のリアルな生活を知りたいあなたにオススメです!
とある留置場 僕の91日間勾留記(前編)ショックと緊張の一週間
♦︎シリーズ第1弾「ショックと緊張の一週間」♦︎
ある日突然逮捕された主人公。想像もできない留置場という環境の中、襲いかかるショックと緊張の日々――。そんな非日常の中で出会った、“同じ境遇”の人々。無機質な空間で生まれる、かけがえのない絆。だが、別れはいつも唐突にやって来る――。

とある留置場 僕の91日間勾留記(中編)留置場の個性的な人々
♦︎シリーズ第2弾「留置場の個性的な人々」♦︎
ショックと緊張に満ちた一週間を経て、物語は“留置場の人間模様”へ――。そこで主人公を待っていたのは、一癖も二癖もある人々との出会いと、数々のエピソード。
長期勾留がもたらす苦悩と、保釈への希望。そして、その狭間で揺れる絶望。
前作同様、息をのむ展開から目が離せない中編――ぜひご覧ください!

とある留置場 僕の91日間勾留記(後編)留置場内トラブル
♦︎シリーズ最終章「留置場内トラブル」♦︎
「とある留置場」シリーズ、ついにフィナーレを迎える。
保釈で一度は日常へ戻った主人公。しかし、一度訪れた平穏な日常は長くは続かず、1か月後には運命の再逮捕。再び留置場の扉が開く。そこに待ち受けていたのは、過去に例を見ないトラブルと、複雑に絡み合う濃密な人間模様。限界に追い込まれ揺れ動く心、出口なき先の絶望——
シリーズ最終章、もっとも過酷な「最後の留置場」生活がここに!