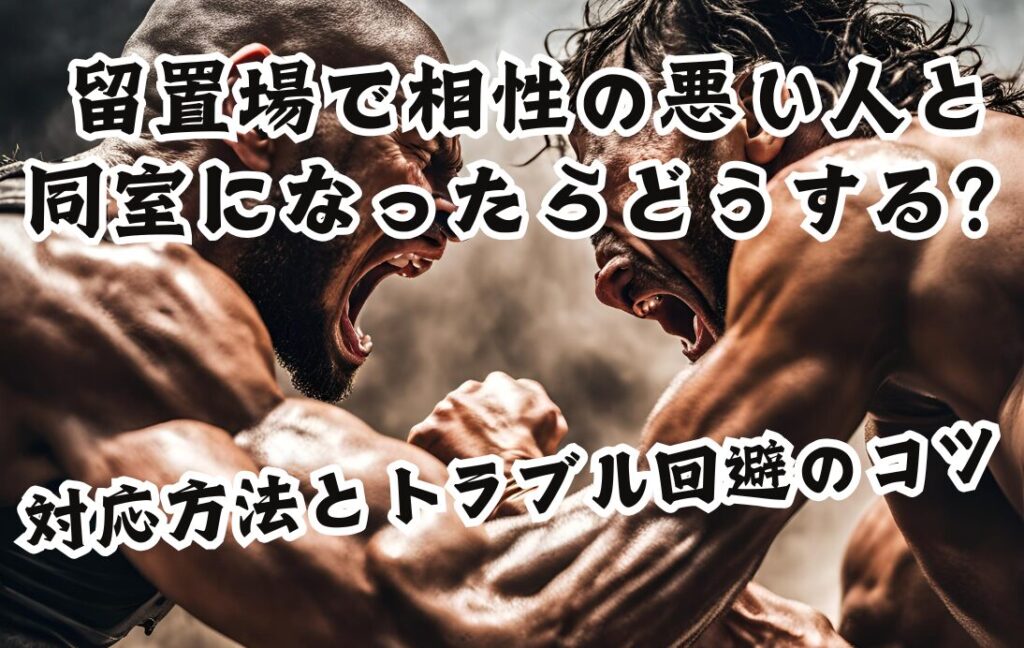- 「留置場から地検や裁判所へはどうやって行くの?」
- 「護送バスってどんなバスなの?」「どんな人が乗っているの?」
- 「車内はどんな構造になっているの?」
このような疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。
留置場に勾留された被疑者が、地検や裁判所へ移送される際に利用されるのが「護送バス」です。この記事では、護送バスの内部や特徴、利用の流れなどについて解説していきます。
護送バスとは?
護送バスは、被疑者や被告人を留置場から地検や裁判所へ安全に移送するための特殊な車両です。
起訴後に留置場から拘置所へ移送される際にも用いられます。
一般的に「護送車」と呼ばれ、外見は普通のバスに似ていますが、内部構造や設備に大きな違いがあります。
護送バスの特徴
- 外観
- 一般のバスに似た外観で、目立たないデザインを採用しています。
- 屋根に警光灯を装備していますが、通常時は使用しません。
- 窓
- 窓にはスモークフィルムが貼られ、外からの視線を遮断します。
- 窓の外側には鉄格子が設置され、逃走を防止します。
- 内部構造
- 運転席と後部座席が金網で物理的に遮断されています。
- 各座席に座っている際は全員両手に手錠を嵌め、かつロープで結束して、被疑者・被告人の逃走を防止しています。
- 少年や女性の顔を隠すためのカーテンを装備しています。
- セキュリティ
- ドアの外側両方にかんぬきを装備し、セキュリティを強化しています。
- 車内に監視カメラが設置されています。
- 大型や中型の護送車場合は、運転席部分に2名(運転手1名と助手席に(書類係)1名)、被疑者が乗車している後部座席部分に警察官2名、合計4名の警察官が監視と逃走防止のために配備されます。
- 小型の護送車の場合は、運転手1名、被疑者の両隣を挟む形で警察官2名、合計3名の警察官が監視と逃走防止のために配備されます。
護送バスの種類
護送バスには主に3種類あります:
- 小型護送車(ノアやセレナなどのミニバンベースが多い):主に単独で地検・裁判所に移送する時に使用する。逮捕時にも利用される。
- 中型護送車(シビリアンなどのマイクロバスがベース):人数が少ない時に使用する。
- 大型護送車(9mクラスの中型バスがベース):警視庁管内では、基本的にはこちらを利用し、複数の警察署を回って被疑者を載せ、地検・裁判所に移送している。
大事件の被告人を護送する場合、大型車一台に一人(と護送担当)を乗せることもあります。
護送バスでの移動:知っておくべきこと
- 乗車人数
- 通常、複数の被疑者が同乗します。起訴後の被告人が乗ることもあります。
- 一人だけで乗車することもあります。その場合は、小型車両を用います。ですが、ごく稀に重大な犯罪を犯した被疑者の場合は、大型車両が用いられたことも過去にはありました(1)。
- 大型護送車の場合、20人前後の被疑者を乗せて移送します。
- 乗務員
- 運転手を含め、複数の警察官が、安全確保と逃走防止のため乗車しています。
- 乗車中の注意事項
- 手錠をかけられ、他の被疑者と共にロープシートで結束された上で、シートベルトを装着します。
- 他の乗車者との会話は禁止
- 他の乗車者と目を合わせることも禁止
- 窓から外を見ることは可能ですが、窓ガラスにスモークフィルムが貼ってあるため、外からは見えません。
- 移動ルート
- 各警察署を回るが、どの警察署を回るか、系統別に分かれている。
- セキュリティ上の理由から、具体的なルートは非公開となっているが、系統が決まっているため、同じような道を毎日運行している。
- 通常、最短ルートを選択して運行している。
- 所要時間
- 留置場から地検や裁判所までの距離によって異なります
- 東京の場合、通常1時間〜2時間程度かかります。
護送バスの車内:どんな雰囲気?
護送バスの車内は、一般のバスとは全く異なる独特の雰囲気があります:
- 厳重なセキュリティ
- 運転席と後部座席が金網で物理的に遮断されています。
- 各座席に手錠が常備されており、被疑者・被告人は拘束された状態で座ります。
- 静寂な空間
- 乗車者同士の会話は禁止されているため、非常に静かな環境です。
- エンジン音や道路の音以外はほとんど聞こえません。
- 閉鎖的な雰囲気
- 窓にはスモークフィルムと鉄格子が設置されており、外の景色は見えにくくなっています。
- 少年犯罪のプライバシー保護目的でカーテンが装備されており、それを閉めた場合は、さらに閉鎖感が強まります。
- 緊張感
- 警察官が同乗し、常に監視している状態です。
- 被疑者・被告人は不安や緊張感を強く感じる環境です。
- 簡素な内装
- 座席は硬く、快適性よりも機能性が重視されています。
- 装飾はほとんどなく、必要最小限の設備のみが備わっています。
このような特徴により、護送バスの車内は非常に特殊で緊張感のある雰囲気となっています。
移送中のエピソード:不安やトラブルはある?
留置場経験者の話から、移送中には以下のような不安やトラブルが起こることがあります。
- 心理的ストレス
- 窓から外が見えるため、外界との隔絶を実感しやすく、閉塞感を感じやすいそうです。
- 他の被疑者との接触を避ける配慮がされているが、緊張感は残るそうです。
- トラブル例
- 体調不良になる人がいるそうです。よくあるのが、車酔い。隣に座っている人が嘔吐した際は悲劇だそうです。また、風邪をひいている人が隣にいるときも、至近距離で咳や鼻を噛んでいるなど、感染が怖いそうです。
- パニックになる人が稀にいるそうです。特に地検や裁判所での待ち時間が長くなった時に起こりやすいそうです。地検出発が20時近くになった時は、車内で言葉も不明瞭になるほど錯乱したケースがあったそうです。
- 同じ事件関係者が乗る場合、通常は同乗しないように配慮されます。万が一の情報共有や証拠隠滅の口裏合わせを防ぐ目的だそうです。※例外も耳にしていますが。
地検・裁判所到着後の流れ
- 地検到着後
- バスの到着順に下車していきます。
- 同行室に案内されます
- 概ね9時〜17時くらいまで同行室で待機します。
- 検事調べや、裁判所での勾留質問が長引いた場合は、さらに長時間同行室で待機することがあります。19時くらいまで待機した事例を確認しています。
- 裁判所
- 警視庁管轄の場合は、一度地検に行き、集団同行室で待機後、改めてバスで裁判所に行きます。
- 同行室に案内されます。
- 勾留判断の場合は、同行室での待機中に、黙秘権や弁護士選任権についての説明があります。
- 順番で、勾留質問や公判に呼ばれます。
まとめ:護送バスは、被疑者移送のための特殊車両
この記事では、護送バスの内部構造や特徴、利用の流れなどを解説しました。
護送バスは、被疑者の移送に特化した特殊な車両であり、安全確保のために様々な工夫が凝らされています。
【関連記事】
留置場での勾留中に必ず、管轄の地方検察庁(地検)に行き、同行室に入り、検事による調べを待つことになります。 留置場勾留中に必ず行く地検の同行室とはどのような所なのか? 東京地方検察庁(東京地検または地検)の同行室を例にお …
【留置場生活のリアルを知れるおすすめの書籍】
当サイト管理人による著作。留置場のリアルな生活を知りたいあなたにオススメです!
とある留置場 僕の91日間勾留記(前編)ショックと緊張の一週間
♦︎シリーズ第1弾「ショックと緊張の一週間」♦︎
ある日突然逮捕された主人公。想像もできない留置場という環境の中、襲いかかるショックと緊張の日々――。そんな非日常の中で出会った、“同じ境遇”の人々。無機質な空間で生まれる、かけがえのない絆。だが、別れはいつも唐突にやって来る――。

とある留置場 僕の91日間勾留記(中編)留置場の個性的な人々
♦︎シリーズ第2弾「留置場の個性的な人々」♦︎
ショックと緊張に満ちた一週間を経て、物語は“留置場の人間模様”へ――。そこで主人公を待っていたのは、一癖も二癖もある人々との出会いと、数々のエピソード。
長期勾留がもたらす苦悩と、保釈への希望。そして、その狭間で揺れる絶望。
前作同様、息をのむ展開から目が離せない中編――ぜひご覧ください!

とある留置場 僕の91日間勾留記(後編)留置場内トラブル
♦︎シリーズ最終章「留置場内トラブル」♦︎
「とある留置場」シリーズ、ついにフィナーレを迎える。
保釈で一度は日常へ戻った主人公。しかし、一度訪れた平穏な日常は長くは続かず、1か月後には運命の再逮捕。再び留置場の扉が開く。そこに待ち受けていたのは、過去に例を見ないトラブルと、複雑に絡み合う濃密な人間模様。限界に追い込まれ揺れ動く心、出口なき先の絶望——
シリーズ最終章、もっとも過酷な「最後の留置場」生活がここに!