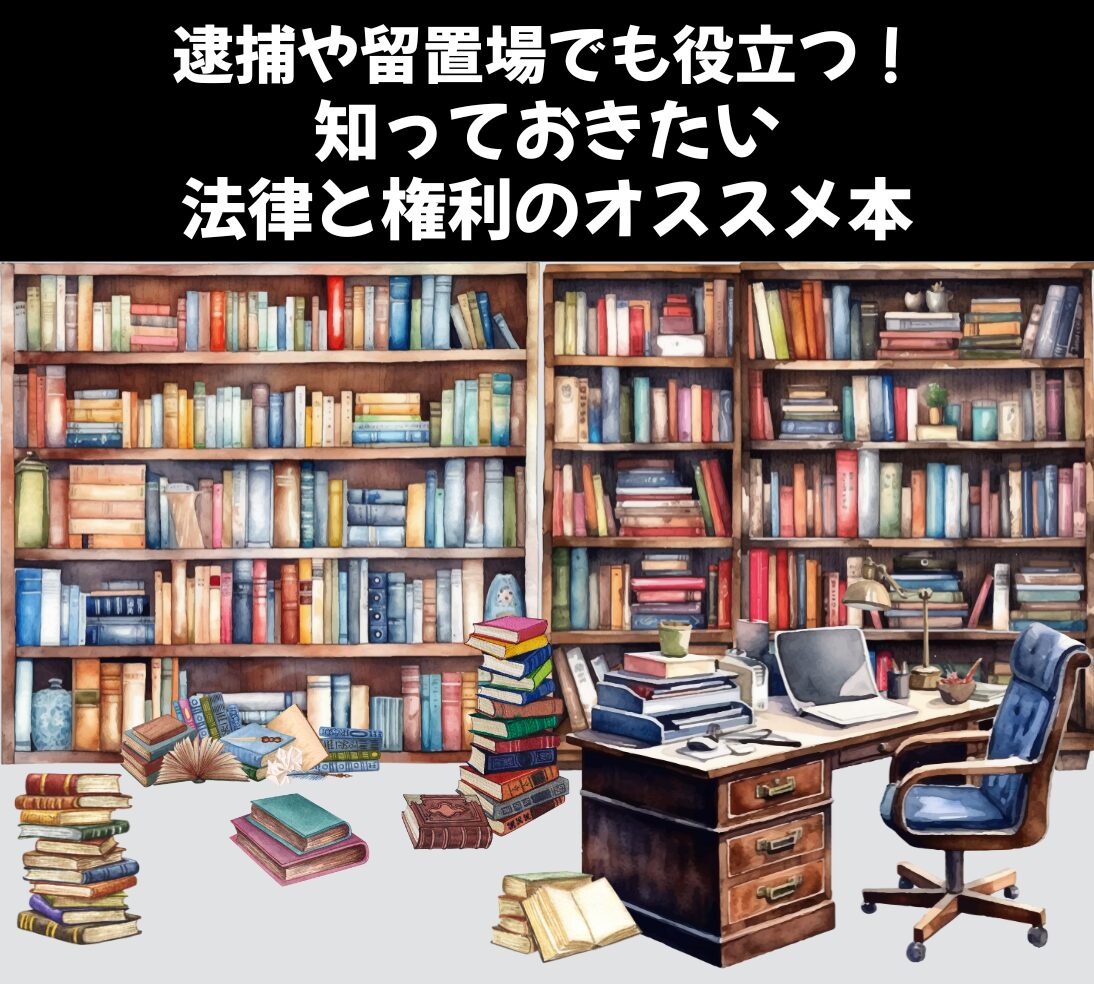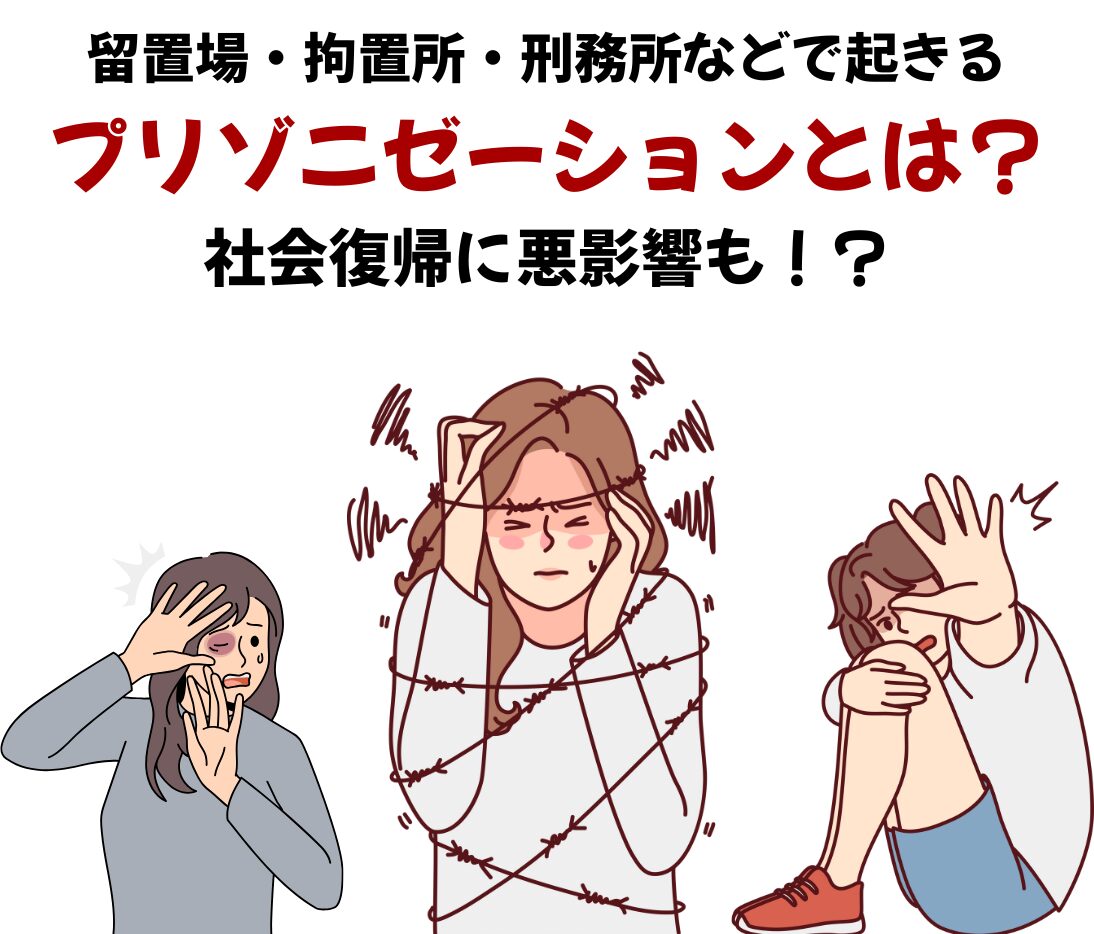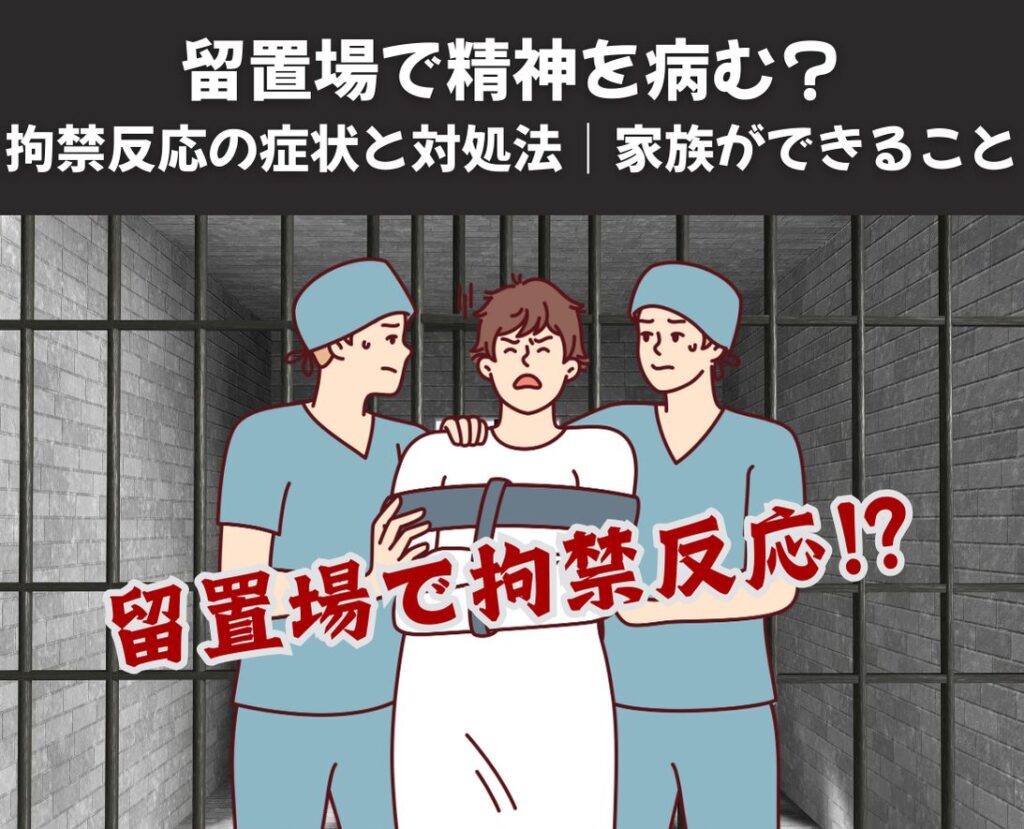
「家族が留置場に入ってから様子がおかしい…」
「留置場で精神病になったりしないだろうか?」
「面会に行ったらひどく落ち込んでいて心配…」
「拘禁反応って何?」
「自白の強要とかあるの?」
留置場で勾留されることは、精神的に大きな負担を伴う経験です。
この記事では、留置場における心理的な影響、いわゆる「拘禁反応」について詳しく解説します。
また、その影響を最小限に抑えるための方法や、家族や知人が支援する際に知っておくべきポイントについても触れていきます。
留置場とは? 精神的な負担が大きい環境
まず、「留置場」とは何かを簡単に説明します。
留置場は、警察署などの警察施設に併設されており、逮捕後、起訴されるまでの被疑者を一時的に拘束する場所です。
自由が大きく制限された閉鎖的な環境であり、精神的な負担が大きい場所と言えます。
また、留置場は代用監獄として使用される場合もあります。
代用監獄については今後の記事で詳しく解説いたします。
👉詳しくはこちら>>留置場とは? 知っておきたい基本情報と疑問を徹底解説
今後の記事>>留置場と代用監獄の関係について
拘禁反応とは?
「拘禁反応」とは、身体の自由を拘束されたことによって引き起こされる精神的な反応の総称です。
留置場に限らず、刑務所や拘置所、精神科の閉鎖病棟など、拘禁されている場所で起こりうる症状です。
主な症状は以下の通りです。
拘禁反応の主な症状
- 原始反応:感情の爆発など
- ヒステリー状態:幻聴、幻覚、興奮
- 慢性妄想:無罪妄想、被害妄想
- 気分障害:抑うつ、躁状態
- 神経症状態:精神衰弱的状態
これらの症状は、勾留期間や個人の性格によって異なります。
拘禁反応の原因とメカニズム
拘禁反応の主な原因とメカニズムは以下の通りです:
- 自由の抑圧:強制的に自由を制限される環境に置かれることで、精神的ストレスが生じます。
- 社会との文化的格差:刑務所内と社会との文化的な隔たりが広がり、適応不安を引き起こします。
- 恐怖と不安:感染や危険に対する恐怖感、先行きの見えない不安感が拘禁反応を引き起こす要因となります。
- 環境の急激な変化:日常生活から突然隔離された環境に置かれることで、心理的な不適応が生じます。
- 長期的な拘束:長期間にわたる拘束状態が、人格の変化や精神状態の悪化を引き起こします。
これらの要因が複合的に作用し、個人の性格や状況に応じて様々な症状として現れます。拘禁反応は、環境の変化に対する心理的・生理的な適応反応として捉えることができます
拘禁反応によるリスク
拘禁反応が重度化すると、以下のような深刻なリスクを伴うことがあります:
- 自傷行為や自殺願望の増加
- 無実の罪への自白をしてしまったり、捜査機関に有利な調書への署名をしてしまう。
- 長期的な精神疾患の発症(例:PTSD)
- 社会復帰への障害
これらのリスクは、早期の対応や支援によって軽減することが可能です。
留置場で拘禁反応が起きやすい原因
留置場で拘禁反応が起こりやすい主な要因は以下の通りです。
- 自由の急激な制限:突然自由を奪われ、行動を厳しく制限される環境に置かれることで強い精神的ストレスが生じます。それが拘禁反応を引き起こすきっかけとなり得ます。
- 社会との隔離(閉鎖的な環境):留置場内と外部社会との完全な隔たりが、適応不安を引き起こします。
- 不安定な状況:留置場での勾留は被疑者または起訴されていても未決囚であり、捜査の進捗や裁判の結果への不安が精神状態に影響を与え、拘禁反応を誘発しやすいと言えます。
- 長期間の拘束:拘束期間が長くなるほど、拘禁反応のリスクや程度が高まりやすくなります。再逮捕などで長期勾留されている被疑者に拘禁症状が強まりやすい印象があります。
- 環境の急激な変化:日常生活から突然隔離された環境に置かれることで、心理的な不適応が生じやすくなります。
- 将来への不安:特に重罪の被疑者や死刑囚の場合、刑の執行への恐怖や不確実な将来への不安が大きな要因となります。
これらの要因が複合的に作用し、個人の性格や状況に応じて様々な拘禁反応の症状として現れる可能性があります。
留置場経験者のヒアリングから感じる、留置場だからこそ拘禁反応が起きやすい原因
また、留置場での勾留経験がある人間へのヒアリングを通じて感じたことは、留置場にいる人こそ拘禁反応が出やすい印象があります。おおむね以下のような話が特徴的です。
- 外部との完全な遮断:仕事・家族・社会復帰・量刑・取り調べへの強い不安
- 仕事も電話も全て禁止された退屈な時間:目的・目標がなく、ひたすら不安に耐えることを強いられる。
- 規則に強制的に縛られる環境:刑務所ではないのに、犯罪人扱いされる。
- 自白を求められる環境:容疑を認めないと、執拗な取り調べがあったり、保釈されない実質的な「人質司法」による自白が強要されやすい環境
とても不安を感じやすい状況だということがわかります。
拘禁反応やプリゾニゼーションが起きやすい環境です。
逆に刑務所は刑務作業があるので、目的・目標があるため、比較的安定しやすいのではないかと推測しています。
諸外国に比べて圧倒的に長く勾留される日本の留置場(代用監獄)だからこそ起こり得るものと言えます。
拘禁反応と自白強要の関係
拘禁反応と自白強要には密接な関係があります。
- 長時間の取り調べや心理的圧力は、拘禁反応やプリゾニゼーションを引き起こす要因となり、意図せずとも、自白を強要したり、無実の罪での自白を誘発してしまう手段となります。
- 拘禁反応の一種である「ガンゼル症状群」は、被疑者が現実逃避のために不適切な回答をする状態を指し、留置場による長期間の勾留の結果生じ、無実の罪に対しての自白調書が作られてしまう原因になる可能性があります。
拘禁反応は被疑者の精神状態を不安定にし、自白を強要するような取り調べに対して精神的脆弱さを喚起し、無実の罪なのに自白させてしまう可能性があります。そのため、えん罪のリスクが。
留置場での勾留による拘禁反応と自白強要は誰にでも起こり得る。冤罪も作られる。
やってもいない犯行を自白する心理
- 逮捕・勾留のストレス(拘禁反応またはプリゾニゼーション):
心理学の実験で、「囚人実験」というものがあります。これは内容や目的を理解して自発的に参加した、心身ともに健康な一般人を模擬監獄に収容して行われた実験です。
「当初2週間の予定」だった実験が、心理的身体的に危険であると判断され、「たった3日で中止」されてしまいました。
模擬監獄でもこれだけの影響があることを鑑みると、留置場での影響がいかに大きいかがわかると思います。 - 現代人にとって、逮捕・拘禁(勾留)自体が拷問のような苦しみであること(推定有罪の国):
留置場による勾留で、無実の罪を自白させられてしまった「足利事件」では、取り調べ開始からたったの13時間ほどで、偽りの自白をしてしまったと言います。
それだけ、取り調べ段階での勾留には慎重にならざるを得ません。
留置場が代用監獄と呼ばれ、捜査段階での長期勾留が先進国で唯一行われており、国連拷問等禁止委員会などの国際機関から再三勧告を受けている背景がここにあります。 - 自白を重視し、強要する捜査機関(警察・検察):
戦前から続いている自白偏重の司法制度と捜査手法が、長期勾留と拘禁反応やプリゾニゼーションなどを引き起こしているだけでなく、人権を無視した自白を強要する取り調べも多数取り上げられています。
例えば以下のような事件があります。- 2018年の犯人隠避教唆事件で、黙秘権を行使する被疑者に対して、約20日間で合計56時間以上の取り調べを受け、その間に屈辱的な言葉を浴びせられたと主張したものです。この取り調べにより「黙秘権を侵害された」として、国に損害賠償を求める訴訟を起こしました。
具体的には「子供じゃないんだから」とか「超筋悪。まさに刑事弁護を趣味でしかやれない人」「もともと嘘つきやすい体質なんだから、あなたは」「社会性が欠けてる」などの不適切な発言が取り調べの録音・録画によって明らかになり、2024年1月にその画像が公開されました。
裁判の結果、国家賠償請求訴訟で取り調べが違法だと認定されたものです。 - 2003年の志布志(しぶし)事件は、選挙で当選した県議が支部市長の集落の住民に現金を配ったとして、公職選挙法違反の容疑で、住民が逮捕されたものです。
長期間の逮捕・勾留による不安や、執拗な取り調べで住民6名の「なかった事実を認める虚偽の自白調書」が作成されてしまいました。
裁判では逮捕・勾留された住民11名全員が容疑を否認しました。3年半に渡る審議の結果、住民全員に無罪判決が出たものです。
人質司法・代用監獄による自白強要の良い事例だと思います。
- 2018年の犯人隠避教唆事件で、黙秘権を行使する被疑者に対して、約20日間で合計56時間以上の取り調べを受け、その間に屈辱的な言葉を浴びせられたと主張したものです。この取り調べにより「黙秘権を侵害された」として、国に損害賠償を求める訴訟を起こしました。
- 検察の言い分を丸ごと認める裁判所の体質:
自白偏重が起きやすいもう一つの要因に、裁判所もその体質に追随していることです。検察からの被疑者の留置場への勾留請求については、元々は99%以上認めていて、最近でも95%は認められていると言われています。さらに自白を強力な証拠資料として用い、その根拠については検察の言い分を丸ごと認める傾向が強いと言われています。司法全体として冤罪が起きやすいと言えるでしょう。
これら司法の問題や、留置場で起きているリアルな現状について知りたい方は下の記事がおすすめです >>
法律のトラブルはある日突然やってきます。準備なしにそのトラブルに巻き込まれると、金銭的にも精神的にも大きなダメージを負ってしまいます。法律や権利について知識を得ておくことは、自らの身を守ることにもつながります。法律や権利、日本の司法制度などについて考えるきっかけになる本を選んでみました!ぜひ参考にしてみてください!
日本における冤罪
以下に、日本の有名な冤罪事件とその簡単な概要を列記します:
- 免田事件:1948年の強盗殺人事件。免田栄さんが死刑判決を受けたが、再審で無罪となった日本初の事例。
- 財田川事件:1950年の強盗殺人事件。谷口繁義さんが死刑判決を受けたが、再審で無罪となった。
- 松山事件:1955年の殺人・放火事件。斎藤幸夫さんが死刑判決を受けたが、再審で無罪となった。
- 島田事件:1954年の幼児強姦殺人事件。赤堀政夫さんが死刑判決を受けたが、再審で無罪となった。
- 袴田事件:1966年の強盗殺人放火事件。袴田巌さんが死刑判決を受け、48年間拘束された後、再審開始決定により釈放された。
- 松川事件:1949年の列車往来妨害事件。20名が逮捕されたが、全員が無罪となった戦後最大の冤罪事件。
- 帝銀事件、三鷹事件、名張毒ブドウ酒事件:いずれも死刑判決が出された冤罪の疑いがある事件。
- 飯塚事件:1992年の女児殺害事件。死刑執行された後、DNAの再鑑定により冤罪の可能性が指摘された。
- 足利事件:1990年の幼女誘拐殺人事件。菅家利和さんが無期懲役判決を受けたが、DNA再鑑定により冤罪が判明し、2010年に再審で無罪となった。17年間の服役後、釈放された事例。
これらの事件は、自白の強要や証拠のねつ造など、捜査機関の不適切な対応が問題視された事例が多く、日本の刑事司法制度の課題を浮き彫りにしています。
拘禁反応に対して、家族や知人ができる支援
拘禁反応を軽減するためには、家族や知人が適切な支援を行うことが重要です。以下は、その具体的な方法です:
- 定期的な面会や手紙の送付 面会や手紙は、孤独感を和らげ、心理的安定をもたらします。
- 法律的サポートの確保 弁護士を通じて、勾留されている本人が安心して対応できる環境を作ることが大切です。
- 心理的なサポート 「あなたのことを心配している」という気持ちを伝えるだけでも大きな支えになります。また、具体的な行動(手紙の内容や面会時の話題)も工夫しましょう。
拘禁反応への本人ができる対処法
- 面会や差し入れの活用:家族や友人との接触は精神的な支えになります
- 弁護士との連携:法的サポートを受けることで不安を軽減できます
- 知り合いの弁護士がいないときは、こちらの記事をご参照ください >> 逮捕後に困らない! 初めての弁護士選びと賢い活用法
- 精神安定剤の利用:医師の処方があれば、精神的な辛さを和らげるための薬を利用できる場合があります。留置場で設けられている医師の診察時に相談しましょう。
- 読書や運動の活用するなど楽しみを作る:許可された本を読んだり、運動時間を有効活用したりすることで、精神的な安定を保つことができます
- 手紙のやり取り:家族や友人との手紙のやり取りは心の支えになります
- 生活リズムを整える:起床や就寝の時間を守り、規則正しい生活を心がける。
- ポジティブな考えを持つ:小さな目標を立てたり、趣味に没頭することでストレスを軽減します。
- 支援を求める:心理的に辛い時は、弁護士や留置担当官に相談することが重要です。
拘禁反応の長期的な影響と社会復帰
勾留期間が長期化すると、拘禁反応が社会復帰に悪影響を与えることがあります。以下のようなサポートが必要です:
- 心理カウンセリングや治療
- 就労支援や社会復帰プログラム
- 家族や地域社会からの支援
これらの支援については、今後の記事でさらに詳しく取り上げる予定です。
まとめ:拘禁反応は誰にでも起こりうる
拘禁反応は留置場での生活で生じる可能性がある心理的・身体的反応です。ですから、特殊な人がかかるものではなく、誰にでも起こりうるものです。特に逮捕のショックが強く、将来や取り調べへの不安が強いうえに、何もすることのない留置場生活では特に起きやすいものと言えます。
家族や知人が勾留されている場合は、面会や差し入れを通じてサポートすることが重要です。また、自首を考えている方は、事前に弁護士に相談し、心の準備をしておくことをおすすめします。
留置場に関する疑問や不安がある場合は、専門家のアドバイスを受けることが大切です。適切なサポートと対策により、拘禁反応のリスクを軽減し、より良い状態で勾留期間を過ごすことができるでしょう。
もし、家族や知人が留置場で精神的に不安定な様子であれば、早期に弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
【関連記事】
プリゾニゼーションとは プリゾニゼーション(Prisonization)は、留置場や拘置所などの拘禁施設や刑務所などの厳しい環境に適応する過程で、収容者が個性や積極性を失い、従属的で受動的な行動を取るようになる現象を指し …